企業をさがす
企業をフォローすると、興味のある/志望度の高い職種にマッチする募集情報をお届けします。新たな募集が公開された際だけでなく、すでに公開中の募集がある場合も通知を受け取ることができます。

【かぎりあるものから無限を創ろう】 1884年の創業以来、非鉄金属に関わる技術の力で社会に貢献してきたDOWAホールディングス。 金属の製錬から加工、リサイクルまで、資源循環の全側面に関わる一方、展開する多彩な事業領域では独創的なインフラを駆使し、数々のニッチトップ製品を生み出しています。 ◆事業 ・環境リサイクル(廃棄物処理、リサイクル、汚染土壌回復) ・資源開発・非鉄製錬 ・電子材料、半導体材料、磁性材料、情報・通信関連 ・金属加工(伸銅品、めっき) ・熱処理加工・熱処理設備(設計、製造、販売) ◆DOWAの特徴(1) 資源循環型事業 1970年代からいち早く環境・リサイクル事業に取り組み、資源循環型社会の構築に貢献してきました。鉱山開発・製錬や、素材の高付加価値化を進め、さらには、さまざまな製品に使われ廃棄された後も、有価な金属を回収するリサイクルを手がけています。廃棄物の無害化、減容化にも取り組み、広く持続可能な社会の実現に向け「資源循環型事業」に取り組んでいるのがDOWAです。 ◆DOWAの特徴(2) ニッチトップ ニッチとは、他社が手を出さないような領域のこと。DOWAは他社がまねできないような、技術力の高いモノを提供することで、先駆的に市場を開拓してきました。例えば、半導体材料になる「高純度ガリウム」や太陽電池に使われる「銀粉」などは国内外でトップシェアを誇ります。 もっとDOWAの特徴を知りたい方は、お急ぎの方向け キーワードで知るDOWAのページをご覧ください! https://www.dowa.co.jp/saiyou/beginner/

「マテリアル」と聞くと、素材・材料とイメージされるかもしれませんが、私たちは、非鉄金属をはじめとする基礎素材だけでなく、自動車や家電などに使われる機械部品や電子材料・部品、それらを作るために必要な道具(超硬工具)も製造・販売し、さらにクリーンエネルギーや環境リサイクル事業も行う「総合素材メーカー」です。 創業から150年以上にわたり、時代とともに変化する社会のニーズに応えるべく、経営の多角化や事業の拡大を続けながら発展してきました。現在は、「次世代自動車」「IoT・AI」「持続可能な豊かな社会の構築」を新製品・新事業を創出する柱として捉え、事業戦略を策定しています。 新たな「マテリアル」を創造するために、私たちは挑戦を続けます。 【事業内容】 ●機能材料・化成品・電子デバイス等の製造・販売 ●超硬切削工具の製造・販売 ●銅・金・銀等の製錬・加工・販売 ●地熱・水力・太陽光・バイオガスの発電 ●家電・自動車部品・リチウムイオン電池・焼却飛灰のリサイクル など

------------------<INPEXの使命>------------------------ 私たちINPEXは、日本最大規模のエネルギー開発企業として、これまで石油や天然ガスの探鉱・開発・生産という上流事業を中核として発展してきました。今後も増加する国内外のエネルギー需要に応えるため、石油・天然ガス事業の徹底したクリーン化を進めながら安定供給の責任を果たしていきます。さらに昨今の気候変動問題や低炭素化に対応し、2050年ネットゼロカーボン社会の実現に向けて、CCS・水素・アンモニアを中心とした低炭素化ソリューションや、再生可能エネルギー、電力事業など、新たな技術分野への取り組みをより加速させていきます。 ------------------<ネットゼロカーボン社会に向けた取り組み>------------------------ INPEXでは2050年ネットゼロカーボン社会の実現に向けて、2025年2月に新たにINPEX Vision 2035 「責任あるエネルギー・トランジション」の実現を策定し、より低炭素なエネルギーの安定的な供給と、持続可能で地球環境に配慮した「責任あるエネルギー・トランジション」のため、以下の3つの成長軸を掲げています。 1. 天然ガス/LNG事業の拡大 2. CCS/水素をコア技術とした低炭素ソリューションの提供 3. INPEX「ならでは」の強みを活かしたエネルギー・資源分野での新たな挑戦 エネルギーの安定供給においては、石油・天然ガスの上流事業を基盤事業として、天然ガスシフトを進めて国内外におけるグローバルガスバリューチェーンの拡大、さらにはCCSを通じた国内外でのクリーン水素/アンモニア供給の事業化などを推進していきます。 詳細はこちら https://www.inpex.com/assets/documents/company/inpex_vision_2035.pdf ------------------<技術力の強化>------------------------ 【石油・天然ガス開発の技術を活かす】 今までの石油・天然ガスの探鉱・開発事業で培われたコア技術をさらに得意技術に育てていきます。そして既存事業で現在直面している技術課題や、未来の多様化するエネルギー社会を見据えた新技術分野にチャレンジする事で、総合的な技術力の強化を図っていきます。そこには機械工学・電気工学・化学工学など様々な理学・工学バックグランドを持った社内外の技術者と協働してプロジェクトを進めていく必要があります。 開発計画段階では、生産施設の概念検討・設計、基本設計において設計方針を定め、安全面に配慮しながら最適な施設の設計作業を実施・管理します。開発段階では、EPCコントラクターに外注し、詳細設計・調達・建設の各業務について、作業内容の確認やスケジュール管理などを行いながらプラントを建設します。石油・天然ガスは、砂漠や大水深地域で発見されるケースも多く、その性状も各々で異なるため、地域環境や石油・天然ガスの性状に合わせた生産施設を設計・建設していきます。また今後は地熱や洋上風力など再エネ事業に必要な施設や気候変動に対応した施設の設計や建設も行っていく予定です。 生産段階では、安全な操業に加えて稼動率向上(故障の最小化)・設備寿命の延長のための保守作業を行います。また、必要に応じて既存生産施設の増強・改造を計画・実行します。最終的には生産の終了した生産設備の撤去を行います。 さらに、今後はCO2EORによる回収率向上などの技術をコア技術に、また洋上風力発電などの再生可能エネルギーやCCS、CCUSも新たな課題とし、コア技術にすべく取り組んでいきます。 EOR(Enhanced Oil Recovery):原油増進回収法 CCS(Carbon Dioxide Capture and Storage):二酸化炭素の分離回収・貯留 CCUS(Carbon Dioxide Capture, Utilization and Storage):二酸化炭素の分離回収・利用・貯留 【クリーンエネルギー技術の開発と高度化への取り組み】 INPEXでは「長期戦略と中期経営計画(INPEX Vision@2022)」に基づき、技術分野の基盤整備として技術研究所内にクリーンエネルギー技術の開発・高度化に関わるネットワーク拠点として「INPEX Research Hub for Energy Transformation」、通常I-RHEX(アイレックス)を発足しました。 I-RHEXでは、石油・天然ガス開発技術のクリーンエネルギー技術(CCUSや低コスト水素製造、二酸化炭素の回収・利用など)への応用や先進技術の研究・開発を行います。INPEXの技術や人材を活用することに加え、広く企業・大学・研究機関等との連携や協働を通じて広く社会のEX(Energy Transformation)に貢献できる拠点となることを目指しています。 紹介記事はこちら https://rikejocafe.jp/blog/inpex/795 https://rikejocafe.jp/blog/inpex/804
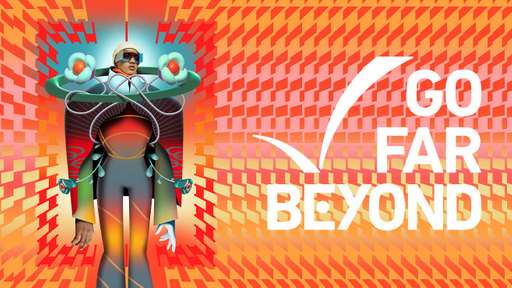
~東証プライム上場の優良企業~ 【会社概要】 当社は四輪/二輪車用向けに、デファレンシャル/トランスミッションギヤ/プラネタリィ/ボールジョイント/カムシャフト等の開発/製造/販売を行っています。 二輪車向けトランスミッションは業界トップクラスの占有率を誇ります。 電動、自動運転といった次世代自動車向けパワートレイン、サスペンション、ステアリング等の商品展開を進める一方、 先端AI技術開発によるインダストリー4.0の推進、SDGsの幅広い領域での達成貢献に向けたオープンイノベーション展開等、広く新事業の創出・拡大にも注力しています。 【事業・商品の特徴】 MUSASHIの歴史、時代の変化に柔軟に対応し、挑戦を続けた歴史。 1938年に航空機部品の製造でスタートした当社ですが、82年の歴史を振り返ると、時代の変化や国際情勢の変化に柔軟に対応しながら、新しい事業に挑戦を続けてきたことがわかります。 1946年ミシン産業参入、1956年二輪車部品製造開始、1967年自動車部品製造開始以降、グローバル化に対応して14か国に事業を展開してきました。 そして、現在は四輪車・二輪車向けの自動車部部品の製造が中心となっていますが、100年に1度と言われる自動車業界の大きな変革期を迎え、「CASE」といった流れに対応するために、 大きな強みを持つコア事業の強化を掲げています。 【事業・製品への取り組み】 当社は、コア事業である自動車部品事業と5つ新規事業で、テクノロジーを追求し、新規事業の創出により社会課題を解決し、 「人と環境が調和した豊かな地球社会」の実現に向けて取り組む企業です。 ①自動車部品事業 当社は、自動車部品の中でも、「走る」「曲がる」の機能に関連した部品を開発・製造しています。 他部品よりも品質が高く求められる「重要保安部品」を扱っており、自動車の中核を担うコア部品を扱っています。 ②e-Mobility事業 インド・アフリカ地域において、スタートアップとの協業により、自社開発e-Axleを搭載したEVスクーターの販売が開始されます。 今後新興国向けに小型モビリティ向けe-Axle事業の拡大を進めます。 ③Energy Solution事業 次世代蓄電デバイスであるHSC(ハイブリッドスーパーキャパシタ)をコアに、事業拡大に取り組んでいます。 新たなマーケットとして、データセンターや鉄道事業者向け電力システム等の事業開発を進めます。 ④Smart Industry事業 AI外観自動検査機、無人搬送車を中心とした製造現場向け自動化ソリューションを展開しています。昨年譲受されたS‐CART事業を加え、事業の拡大を進めています。 ⑤植物バイオ事業 最先端のバイオテクノロジーを駆使した研究開発により、植物の持つ機能性を生かしたヘルスケア商品を提供してまいります。 ■参考資料 Yotubeで会社紹介動画を掲載中! ↓詳しくはこちらから↓ https://www.bing.com/videos/riverview/relatedvideo?q=%e3%83%a1%e3%82%a4%e3%82%ad%e3%83%a3%e3%83%aa%e3%80%80%e6%ad%a6%e8%94%b5%e7%b2%be%e5%af%86%e5%b7%a5%e6%a5%ad&mid=73C90BC8AF5D653C82EC73C90BC8AF5D653C82EC&FORM=VIRE

「価値をつくる。未来をつくる。」 技術で、情熱で、創造力で。 全ての仕事が価値創出につながっている―――― 私たちが考える「価値」とは、人々の暮らしをより良くすることにつながる、あらゆる「もの」や「こと」です。 素材や金属といった目に見える製品だけでなく、サービス、事業構造、経営手法、社員の社会貢献活動など、 形のないものも含まれます。 暮らしを豊かにするものであれば、それはすべて私たちにとっての「価値」なのです。 JX金属の歩みと挑戦 JX金属は2025年、創業120周年を迎えました。東証プライム市場への上場、新拠点の開設など、次の成長フェーズへと進んでいます。 私たちは常に「より良い社会」の姿を見つめ、その実現に向けて価値を生み出し続けてきました。 素材産業にとどまらず、石油精製、エレクトロニクスなど多くの事業領域へ展開してきた背景には、 「その時々に、社会の発展に本当に必要なものを届ける」という一貫した思いがあります。 未来への挑戦 私たちは、変化し続ける社会に向けて、最も効果的な形で価値を届けることに挑み続けます。 現在、半導体材料や情報通信材料の分野でグローバルに挑戦し、世界の技術革新を支えながら、 持続可能な社会の実現に貢献しています。 これからも、社会のニーズを先取りし、未来を切り拓く価値創造に挑戦し続けます。 ━━━━━━━━━━━━━ ■事業概要 ━━━━━━━━━━━━━ JX金属は、銅を中心に、金属そのものを生み出す上流の資源開発から、製錬、下流の先端材料の開発・製造、さらには使用済み製品からのリサイクルに至るまで、上流から下流まで一気通貫の事業を展開しています。 私たちの製品は、スマートフォンやPC、電気自動車(EV)、データセンターなど、現代社会に不可欠なあらゆる製品に内蔵されており、デジタル社会や脱炭素社会の実現を根幹から支えています。 【1】半導体材料セグメント ┗半導体ウェハーの回路形成に不可欠なスパッタリングターゲット(世界シェア約60%)や、タンタル・ニオブなどの高純度金属を供給しています。 【2】情報通信材料セグメント ┗スマートフォンなどに使われる圧延銅箔(世界シェア約80%)や、高機能な表面処理剤、金属粉末などを提供しています。 【3】基礎材料セグメント ┗優良な海外鉱山への投資・開発を行う「資源事業」と、銅製錬および使用済み電子機器などから金属を回収する「金属・リサイクル事業」を展開しています。 ▼ぎゅっと凝縮したので理系学生に見てほしい!会社を深く知れる動画はこちら! ・【27卒向け】JX金属の事業・製品はどう社会を支えている? ⬛︎理系出身の2人が語る!開発・製造・営業を経験した社員によるJX金属の魅力⬛︎ https://www.youtube.com/watch?v=BDcHOJ_qUPM ・技術系職種動画 ■資源~材料プロセス~プラントエンジニアそれぞれの仕事の魅力とは?■ https://youtu.be/oShQtxYPfdw?si=yRm4TRG6pCxNm8jA ━━━━━━━━━━━━━ ■世界シェア80%を誇る製品も。JX金属が誇る、高い技術力 ━━━━━━━━━━━━━ フレキシブル回路基板(FPC)などに用いられる圧延銅箔や、半導体製造に欠かせないスパッタリングターゲットなど、JX金属は世界でも高シェアを誇る製品を数多くつくっています。 製品それぞれに、これまで培ってきた高い技術力が生かされています。 事業における生産能力も特徴の一つ。銅をはじめとする各種製品において、高い生産能力を有しています。 ▼技術力紹介は、ぜひこちらからもご覧ください! https://jx-nmm-recruit.com/about/technology.html ▼主力製品詳細 ・フレキシブル回路基板(FPC)用 圧延銅箔(世界シェア80%) ┗フレキシブル回路基板(FPC)とは、ポリイミドなどの絶縁性を持つ薄く柔らかいフィルムと極薄の銅箔等の有同性金属を貼り合わせた機材に、 電気回路を形成した基盤のことです。 その特徴は「薄く、軽く、そして曲がる」こと。 今日ではスマートフォンや液晶モニター、車載用部品、さらには航空機まで用途は拡大し、「便利で快適な社会」に貢献しています。 JX金属の圧延銅箔はこのFPCに必要不可欠な素材であり、最も薄いもので0.006mm(=髪の毛の約100分の1)と言う、FPC用途では世界一の薄さを誇っています。 ・半導体用スパッタリングターゲット(世界シェア60%) ┗スパッタリングターゲットは、スマートフォンなどに組み込まれる半導体をつくるために欠かせない製品です。 JX金属のスパッタリングターゲットは「銅の純度が非常に高い」ことが特徴。 JX金属は99.9999999%(ナインナイン)と言う世界最高純度の銅をつくる独自の技術を持っています。 その技術を活かし、時代のニーズにこたえる高性能なスパッタリングターゲットを開発、半導体の製造に大きく貢献しています。 ・電子材料向け高純度タンタル粉(世界シェアNo.1) ┗タンタルは、希少性の高い金属であるレアメタルの一つです。 PCをはじめとする電子機器、自動車の蓄電部品(コンデンサー)や半導体などの材料として幅広く用いられており、私たちの生活に不可欠な資源です。 今後、IoT社会の進展によってさらなる需要の伸長が見込まれるほか、航空宇宙およびエネルギー産業においても役立っています。 3Dプリンターで製造される医療機器などの材料としての活用も期待されています。 JX金属は、日本やドイツをはじめ各国の製造・販売拠点を通じて、高品質のタンタル粉を安定的に製造・販売し、IoT社会の発展に貢献しています。 ━━━━━━━━━━━━━ ■『パラデル漫画で知る!あなたの知らない銅の世界』 ━━━━━━━━━━━━━ 動画:https://www.youtube.com/watch?v=DokT8EmmmbA 「パラパラ漫画」と「飛び出す」を組み合わせた「パラデル漫画」のキャラクター「ぱらお」と「ぱらみ」。 二人がジュースを買おうとお金を取り出すと、10円玉が銅の妖精「カッパーくん」に変身!? 銅って何に使われているの? 銅ってどうやって作っているの? 銅のリサイクルってどうするの? 「パラデル漫画」の世界で、「カッパーくん」から銅について学んでみましょう!

事業内容:豆苗(とうみょう)・スプラウトなどの発芽野菜や高成分野菜、 レストラン向けマイクロハーブの生産・販売 新野菜の企画・開発・販売等 ミッション:私たちは「生命(いのち)を守る農ビジネス」をテーマに,新しい価値を創造します。 バリュー:01 カスタマー・ファーストで「考動」 すべてはお客様の健康のために 02 圧倒的なQPSを実現 Quality,Price,Serviceを、「満足」から「感動」へ 03 ハート&ハイテク「脳業」 植物への愛情と科学的合理性で最高の品質を追求 04 「3C」で切磋琢磨 まずChallenge,常にChangeで,Chanceを掴む 05 エンジョイビジネス! 「自考自走」で仕事を楽しむ 当社の事業領域である「農業」は、従来の庇護されるべき「生業」から、 日本の成長戦略の一翼を担うべき「産業」へと今後大きく変貌を遂げようとしています。 こうしたなか、当社は、これまで培ってきた「食の安全性」「品質の高さ」「科学的検証」を 一層追求し続けることを成長の原動力とし、お客さまのこころとからだの健康に寄与する商品を 国内外に普及させることで、その一翼を担いたいと考えています。 「生命を守る......」というミッションは、このような基本認識のもと、 食料生産としての「農」に加え、同じく成長戦略で重要とされる医療、 とりわけ「予防医学」に関連する「農」を事業領域とすることを示したものです。 また同時に、社員が行動規範とすべき5つのバリューを策定することで、 新たな価値を創造し続けていく決意を全社で共有してまいります。

<ビジョン> 科学技術の発展と地球貢献を実現する <ミッション> 地球上で最も効果的な知識製造業を行う企業群になる <コアコンピタンス> サイエンスとテクノロジーをわかりやすく伝える - 研究者ネットワーク: 大学・研究機関との強固なネットワークを持ち、最先端の研究情報・人材にアクセス可能 - サイエンスコミュニケーション: 科学技術を分かりやすく社会に伝えるスキルと実績 - 事業創出力: 研究成果を社会課題の解決や事業化につなげる提案力 <事業内容> 1. R&Dソリューション事業: 企業の研究開発をサポート 2. 人材・教育事業: 理系学生・研究人材のキャリア支援、次世代の科学者育成 3. メディア・サイエンスコミュニケーション事業: 科学情報の発信、出版 4. 投資育成事業: ディープテック領域のスタートアップ支援・投資 リバネスは理系学生にとって、研究成果を社会につなげる力を身につけ、科学の面白さを追求しながら世の中に貢献するキャリアを描ける魅力的な会社です。ぜひ一緒に、科学技術の力で世界を良くしていきましょう。

農研機構(のうけんきこう)は、我が国の農業と食品産業の発展のため、基礎から応用まで幅広い分野で研究開発を行う機関です。 この分野における我が国最大の研究機関であり、職員数約3,200名(正職員のみ)、年間予算950億円(うち運営費交付金645億円)[2023年度決算]。全国各地に研究拠点を配置して研究活動を行っています。 当機構は1893年(明治26年)に設立された農商務省農事試験場にその起源があります。農林水産省の試験研究機関の時代を経て、2001年(平成13年)に独立行政法人として発足しました。以後、数回の統合を経て2016年(平成28年)に現在の「国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構」となりました。 研究開発の成果を社会に実装するため、国、都道府県、大学、企業等との連携による共同研究や技術移転活動、農業生産者や消費者への成果紹介も積極的に進めています。

「半魚人」として、陸と水、自然と社会。その境界に立つ「通訳者」であれ。 水中から空を観たことがありますか? 海に潜り魚の視点で水中から空を見上げてみると、いつもと違う風景を見つけることができます。 大切な地球が永続的であるためには、自然や環境と豊かで安らぎを求める人間のバランスや調和を図るインターフェースコンセプトが大切です。 私たちの使命は、人間社会の論理(陸)と、自然界の論理(水)の両方を深く理解し、両者が共存できる一点を探る「インタープリター(半魚人)」として社会に貢献すること。 防災、環境、水産、インフラ、食。複雑に絡み合う現場の課題に対し、机上の空論ではない、泥臭く本質的な解決策を導き出す。 自然への畏敬と科学的知見を胸に、未来の当たり前を創造する技術者集団です。 ━━━━━━━━━━━━━ ■事業概要 ━━━━━━━━━━━━━ 私たちは、まちや自然のさまざまな場所で調査を行い、人が安心して暮らせる社会と、自然との共生を目指しています。 自然が好き、社会をより良くしたいという思いを持ちながら、日々の仕事に取り組んでいます。 私たちの仕事は、道路や橋などの社会インフラを守り、自然災害からの災害に備え、また自然環境との共生を考え、次の世代にも引き継いでいくことです。これまでに培った技術や知識を活かし、調査・分析から提案、そして報告まで一貫して対応しています。 仕事は、大きく「防災」「環境」「デジタル技術」に分かれますが、それぞれが横断的に関わり合い、解決方法を導きます。 <社会基盤保全> 老朽化が進む道路や橋梁等の社会基盤の劣化の原因を現場に最も近い視点から推定し、地域の安全と安心を守る仕事です。 <防災・減災> 様々なリスクから人と地域を守るため、事業継続計画や地域防災計画の策定、 実効性ある訓練の実施支援などを通じて、防災力・復旧力の高い組織と社会づくりを支援する仕事です。 <国土保全> 頻発・激甚化する土砂災害に対して、ハードからソフトに至るまで総合的な対策を提案し、土砂災害から国民の生命・財産を守る仕事です。 <水工計測> 洪水や高潮、海岸侵食などの水災害から暮らしを守るため、 フィールドにて様々な計測機器を利用して取得したデータの解析・シミュレーションを行い、 治水・防災の高度化への取組みを支援する仕事です。 <自然環境保全> 現地調査を通して、開発や事業に伴う自然環境への影響を適切に把握し、 人間活動と生態系が調和した持続可能な社会を実現すべく、影響提言措置を提案します。 <空間情報> まちづくりや環境保全の基礎となる空間情報を、 UAVやマルチビーム測深、3Dレーザースキャナなど最新技術を用いて計測します。 得られた3次元空間データと情報システムを活用し、”みえる化”することにより、安全・安心の暮らしを支える仕事です。 ━━━━━━━━━━━━━ ■日本ミクニヤの強み ━━━━━━━━━━━━━ 【1】【やりたいことに挑戦できる会社】 挑戦は、自身の成長への第一歩と考えています。挑戦はやりがいと満足ある人生を築き、その一人ひとりの力が会社の発展と社会の未来に貢献します。 技術や計測機器は日々進化していきます。変化に柔軟に対応するためには、様々な挑戦が必要です。 挑戦する気持ちを大切にし、共に成長する会社です。 【2】【仕事への考え方】 私たちの仕事は、インフラ点検、環境調査、防災計画から漁場環境の改善まで、事業領域は多岐にわたります。 自ら現場に出向き、自身の目で調査点検を行い行います。 現場の状況を的確にとらえ、様々な知見を融合させ、「調査・計測」-「解析・分析」-「評価・診断」-「対策・提言」を行います。 【3】【一貫した対応】 業務における一覧のサイクル・・・「営業・提案」-「詳細計画立案」-「現地調査・計画」-「解析・まとめ」-「報告説明・納品」 私たちは、これらの内容を分業ではなくグループにて一貫して対応しています。 プロジェクトの目的を達成するためには、一連の流れやそれぞれでの理解が必要です。目的を正確にとらえ、達成させるために柔軟な対応に努めます。

株式会社スーパーワーム は、スーパーワームを活用した革新的な養殖および加工技術を開発するスタートアップ企業です。 主力製品はスーパーワームを原料とする「油脂」であり、特に バイオ燃料 としての利用を目的とした事業展開を行っています。 私たちのミッションは、スーパーワームの潜在能力を最大限に活用し、環境とエネルギーのサステナビリティを実現 することです。 スローガンである 「世界を救うスーパーヒーローになる」 のもと、持続可能なエネルギー供給を通じて地球規模の課題に挑み、次世代のソリューションを提供していきます。

●事業内容 九州木材工業は、木材保存のエキスパートとして、保存処理木材を活用した幅広い事業を展開しています。 特にエコアコールウッドと不燃木(ふねぎ)は弊社のオンリーワン技術です(詳しくはHPをご覧ください)。 エコアコールウッドの製造・販売: 国産木材を有効活用し、環境に優しい木材保存処理技術「エコアコールウッド」を国内で唯一製造・販売しています。 不燃木(ふねぎ)の製造・販売:国産木材を有効活用し、薬剤の潮解がない高性能な不燃木材を開発し、国土交通大臣認定を取得しました。 これらの技術を世界遺産の厳島神社や国宝の出雲大社等の神社仏閣をはじめ、近代建築ビル、公共建造物等に活用し、木を活かし環境を保全する仕事です。 【主な製品】 ・エコアコールウッド規格品:デッキ材、外壁材、土台、フェンス材、格子材など ・不燃木材(不燃木):内装材 ・個別受注製品:建築資材(パーゴラ、ウッドデッキなど)、土木資材(ガードレール、港湾施設製品など)、文化財建築部材、太陽光発電架台など顧客のニーズに合わせた製品を製造。 【その他の事業】 ・しろあり予防、駆除工事:長年のノウハウを活かし「木材保存」の精神に基づいた施工を行っています。 ・複合柱の開発、納入: 配電線路用の電柱として複合柱を開発し、九州電力へ納入しています。 ・九州電力送配電(株)配電業務委託 ・電力所の除草、しろあり工事、植栽工事及び管理 ・送電線巡視路等の整備と安全に必要な木製ステップバーの製造販売 ・鉄道用枕木、ガーデニング用枕木の製造販売 ・木材の輸入販売(米材、南洋材、欧州材) ・木材の人工乾燥及び熱処理 ●ミッション 九州木材工業は、以下の2つを大きな使命として掲げています。 ①環境を守る・・・ 国産材の利用拡大を通して日本の森林を守り、持続可能な社会とカーボンニュートラルな脱炭素社会の実現に貢献すること。 ②人の命を守る:・・・電気の安定供給を通して人々の生活と命を守ることに貢献すること。(配電事業における使命) これらの事業とミッションを通して、九州木材工業は、環境保全に貢献しながら、人々の安全で快適な暮らしを支えることを目指しています。